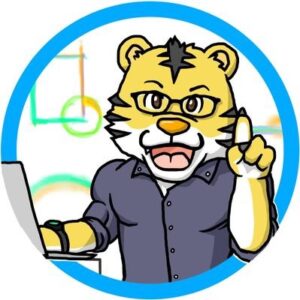
日本には世界的に見ても整っている制度があります。みなさんどんな制度が思い浮かびますか?
そう!社会保障制度です。
細かく見れば行き届いていない、もっと整えるべき箇所は多くあると思います。
病気で働けなくなり、生活に困れば憲法25条が保障している「健康で文化的な最低限度の生活」を全ての国民の権利とし、国の義務として生活保護を受けることができます。
「生活保護」を例えとしましたが、ちば君のブログは『介護』に関しての情報を発信しています。
介護保険サービスを多く利用したときに自己負担部分が何万円にもなると想像したら、利用したいサービスにもブレーキがかかります。
話は医療になりますが、治療目的で入院すると諸々とお金がかかり予想通りまたは予想以上に費用がかかることがあったり、聞いたりした方もいるのではないでしょか?
高額な治療費を支払った後、いくらか戻ってきた。という話も聞いたことありませんか?
これは『高額医療費制度』と言うもので、医療費が高額になった場合、対象となる方へは自己負担額を超えた部分が戻ってくる制度です。
実は介護保険サービスにもこのように、介護サービスを利用し自己負担額が高額になった場合に戻ってくる場合がある制度があります。
それが『高額介護サービス費』です。
今回はこの『介護サービス費』について難しいところは省いて、できる限りここだけは!って言うところを簡単に説明しますので是非最後までご覧ください♪
ー目次ー
介護保険の利用料について
先に、介護保険のサービス利用料の負担について簡単に説明します。
介護サービスを利用すると、利用に応じて、あらかじめ定められた自己負担分を支払う仕組みになっています。
ヘルパーの利用で例えると
| 負担割合 | 自己負担 | 自己負担以外 |
| 1割負担の人がヘルパーを1ヶ月で1万円分利用したら | 1,000円 | 国と市区町村が負担 |
| 2割負担の人がヘルパーを1ヶ月で1万円分利用したら | 2,000円 | 国と市区町村が負担 |
| 3割負担の人がヘルパーを1ヶ月で1万円分利用したら | 3,000円 | 国と市区町村が負担 |
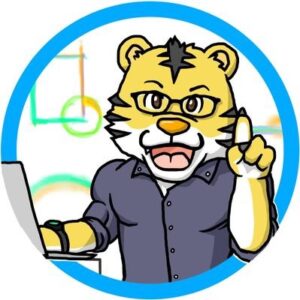
高額介護サービス費をちょー簡単に説明☝️(結論)
高額介護サービス費とは1か月に支払った自己負担の合計が一定金額を超えると、超えた分が払い戻される制度💡
ヘルパーを週2回であったり、デイサービスを週3回、福祉用具の杖や手すりのレンタルを併用している方もいるでしょう。
介護は要介護認定(要介護1など)に応じて介護サービスを1割負担(割合は所得により異なる)で利用でします。
持ち点数以下の1割負担部分が高額になると、人によっては『高額介護サービス費』の対象となり、超えた部分が戻ってくるわけです。
自分の自己負担額がどれくらい上限に達すれば一定金額を超えることになるかは下記の表をご覧ください。
高額介護サービス費による月額限度額(令和3年8月利用分より)
| 区分 | 負担の上限額(月額) | |
| 市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円) | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年集約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 市町村民税課税〜課税所得380万円(770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
| 市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える | 24,600円(世帯) |
| ・合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
・高齢福祉年金を受給している |
24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
|
| 生活保護を受けている | 15,000円(世帯) |
高額介護サービス費の対象となる介護サービス
はじめに💡でお話しした「高額医療費制度」には対象なる部分と対象にならない部分があります。
簡単に説明すると、治療費は対象となり、それ以外は対象になりません。
「高額医療費制度」のように『高額介護サービ費』にも対象となるサービスと対象とならないサービスがあります。
まずは対象となるサービスを紹介します。
訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具など実際に受けている介護サービスについては対象となります。
もう少し具体的な例を出すと
- ヘルパーさんに買い物、掃除などしてもらう
- デイサービスに通い入浴介助、リハビリ指導を受ける
- 福祉用具からベッドや杖を借りる
と、いったサービスが対象となります。
高額介護サービス費の対象外
じゃあ『高額介護サービス費』の対象とならないサービスは?
今先ほど、実際に受けている介護サービスは対象となる。と説明しましたが一部、対象とならないサービスもあります。
- 福祉用具の購入品
- 住宅改修費
- 介護保険の対象でないもの(食費、部屋代、日常生活費(オムツ代など)
福祉用具の購入品
福祉用具の購入品の多くは〝体に直接触れるもの〟がほとんどです。
例えばお風呂の椅子やお風呂の手すり、ポータブルトイレなどがあります。
住宅改修費
要介護認定が下りた方には、自宅をバリアフリーにしたり、階段に手すりをつけたりと自宅をより過ごしやすくするための費用に20万円のまで(うち7〜9割を支給)住宅改修費として援助がでます。
20万円を超える金額に対しては『高額介護サービス費』の対象にはなりません。
介護保険の対象でないもの
1日型デイサービスを利用した際に、昼食を食べる場合があります。その際の「昼食代」には『高額介護サービス費』は適用になりません。
又、ショートステイ(短期間の泊まりサービス)を利用した際には「介護代」+「部屋代(宿泊代)」+「食費代(朝昼夕)」この三つが利用料金となりますが、「部屋代(宿泊代)」+「食費代(朝昼夕)」部分については『高額介護サービス費』は適用になりません。
最後に日用品、オムツ代や歯ブラシなど身の回りの品物についても『高額介護サービス費』は提供されません。
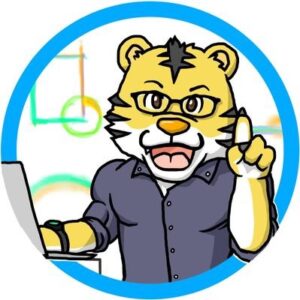
申請方法・支給日(払い戻し時期)
申請方法
『高額介護サービス費』の対象となった場合、自治体(市区町村)から「高額介護サービス支給申請書」が届きます。
必要事項を記入・必要書類を準備して自治体(市区町村)の窓口へ申請します。
本人の身体的な事情等により窓口へ行けない、本人以外が申請(代理申請)することも想定できます。
お住まいの自治体(市区町村)へ申請方法について確認しましょう。
〈注意点〉
申請期間は介護サービスを利用した翌月の1日から2年間です。
自治体(市区町村)により通達の遅い、早いがあるかもしれません。
介護サービスの自己負担額についてはケアマネージャーが管理してます。ひと月の利用が終わった、または見込みで自己負担額をでケアマネージャーへ確認することもできます。
支給日(払い戻し時期)
申請後、約2ヶ月後ほどで希望した銀行へ払い戻しがあります。
「支給決定通知」が届くので併せて確認してくだい。
最後に(まとめ)
僕たちが得する(損しない)社会保障制度は自分達が調べないと得られない制度です。
複雑に複雑が重なり、専門家でない人が全てを把握・理解するのは時間の無駄です。
得する(損しない)制度がある!
と、いうことをなんとなくでも覚えておき、専門家の方へ自分が対象となるのかを聞くと効率がいいでしょう☝️
家族が介護をしていると、時間も体力も気力も奪われてしまいます。
それなのに、複雑な制度を100%理解しようとするのは無理があります。
家族はここぞ!という場面に体力を残しましょう!
『高額介護サービス費』はこちらが積極的になにかしなくてはいけない制度でもありません。
対象となれば、自動で「高額介護サービス支給申請書」が届くので、これを忘れずに申請すればあとは楽です。
役所からの書類は意外と得する(損しない)書類が紛れ込んでいます(笑)
書類に「介護」という文字が書いてあったらケアマネージャーへ確認してもらうをお勧めします💡
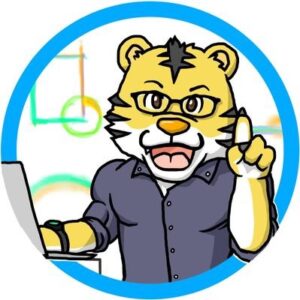
このブログについて🍀
ちば君のブログでは高齢者の老後の満足、介護者の燃焼に役立てる情報を発信しています。
是非、他のブログの記事もご覧になってください♪
また、介護保険についてなにか質問などあれば気軽にお問い合わせください👴👵📞
